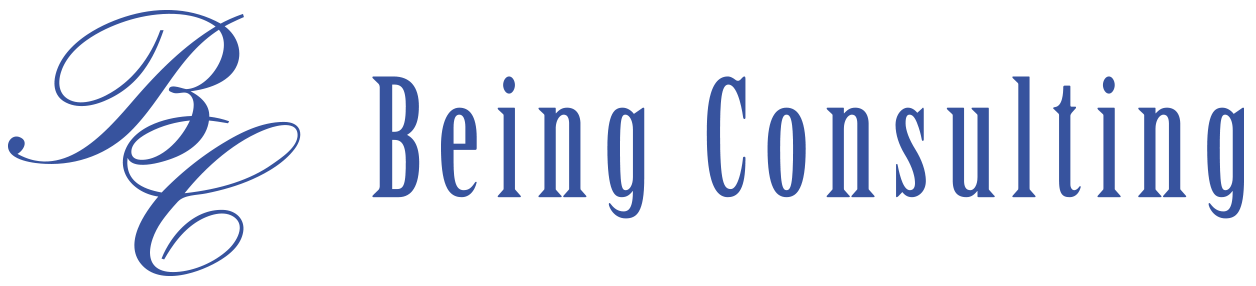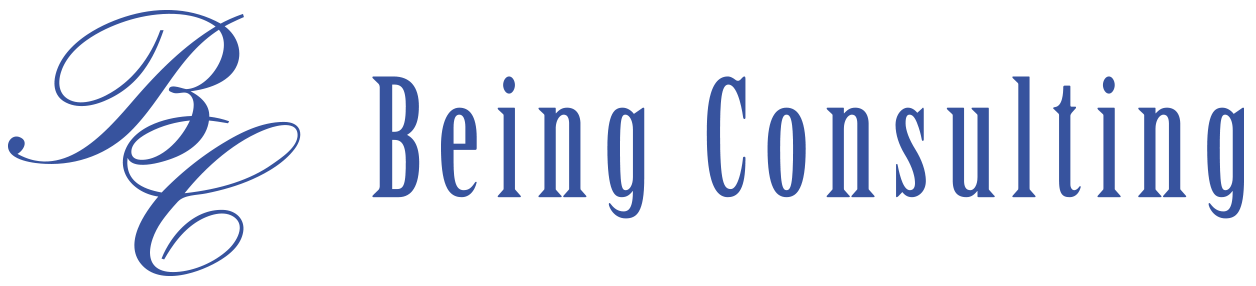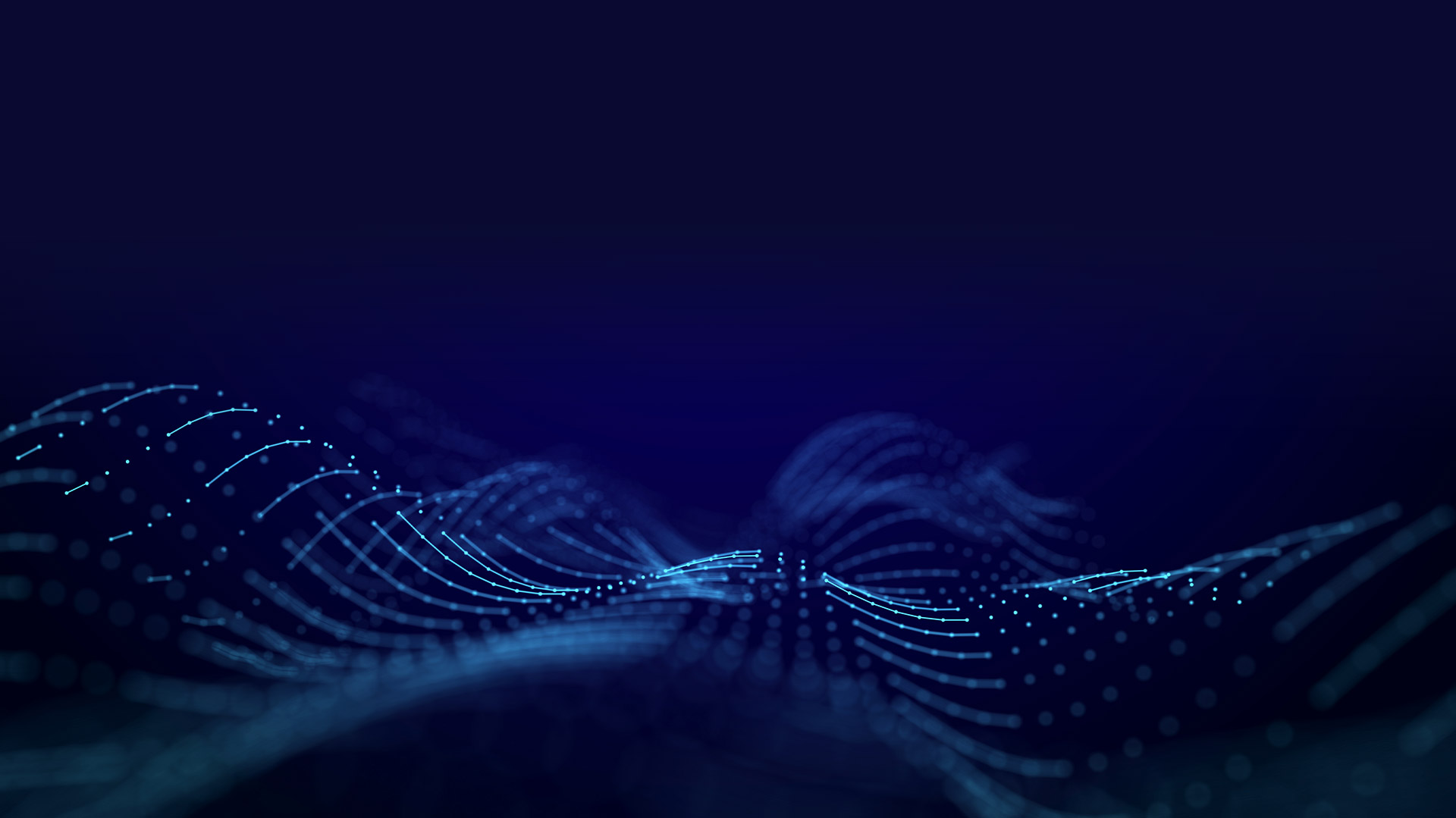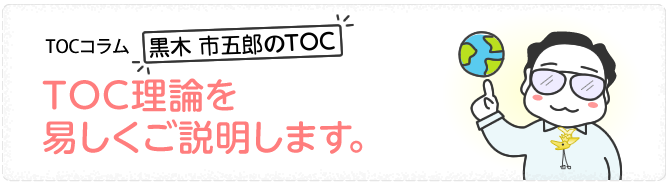
TOC(Theory of Constraints:「制約理論」または「制約条件の理論」)は、
「どんなシステムであれ、常に、ごく少数(たぶん唯一)の要素または因子によって、そのパフォーマンスが制限されている」という仮定から出発した包括的な経営改善の哲学であり手法です。
ここでいうシステムは、通常、工場や部門、会社、団体、行政機関といった組織を指しますが、サプライチェーンや地域コミュニティのように、
単なるひとつの組織でないものを指すこともあります。そして、“パフォーマンスを制限するもの”は、システムの“制約”または“制約条件”と呼ばれ、TOCの名前の由来になっています。
上記から直接読み取れるのは、“制約にフォーカスして問題解決を行えば、小さな変更と小さな努力で、短時間のうちに、著しい効果が得られる”という主張です。
ごく限られた箇所だけを改善または強化すれば、システムとしてのパフォーマンスの向上に直結するからです。その意味で、TOCでは、しばしば、制約を肯定的に“レバレッジポイント”と呼びます。
TOCが他の改善手法と決定的に異なる点は、正に、この制約とそれ以外(非制約)の区別であり、
“この区別を欠いた如何なる努力も決して実を結ばない”というのが、TOCの最も重要なメッセージです。
TOCの提唱者ゴールドラット博士は、その著書The Haystack Syndrome(日本語版「ゴールドラット博士のコストに縛られるな!」ダイヤモンド社)の中で、
制約と非制約の区別を欠いた意思決定が、組織全体に如何に大きなダメージを与えるかについて、
非常に簡単な工場のモデルを使用した思考実験とクイズを用いて、具体的かつ懇切丁寧に解説しています。
また、その中で博士は、特に、制約が新しい場所に移ると、システムはそれまでと全く別ものになると注意しています。
そのときは、以前の制約と非制約を前提にした方針をすべて見直さねばなりません。
さもないと古い方針自身が制約になると警告しています。
そのことは、TOC実践の基本的なフレームワークである「継続的改善プロセス(POOGI:Process of Ongoing Improvement)の5ステップ(5Focusing Steps)」と「思考プロセス(TP:Thinking Process)」が、
「制約の識別」あるいは「何を変えるか?」を最初のステップに位置づけ、繰り返しそこに立ち返えるところに明確に表現されています。
実は、個々バラバラで独立した要素の集まりとして組織を捉える観点からは、そもそも制約と非制約を区別するというコンセプトは生まれてきません。
したがって、組織を相互に関係し依存し合う要素からなる一体のシステムだと捉えることが本質的なのです。
そういう視点を“システム思考(システムアプローチ)”と呼びます。
そのシステムは、自身と外界を隔てる境界を持ち、それ自身の目的があります。そして、その境界を通して外部環境と常に影響し合います。
また、システムが何であるかは、その境界を定めてはじめて決まります。TOCでは、組織をそういうシステムとして捉えることから始めます。